広い空の下、鳥の声を聞きながら園内を散策
狭山公園は、都立狭山自然公園の区域内にある5つの公園のうちのひとつ。南北に細長く伸びていて、南側がふくらんだ「しずく形」をした公園です。
正門のそばにパークセンター(管理所)があります。
今回は、公園の管理や動植物の調査、環境教育などを行っているパークレンジャーの堀内浩揮さんに園内を案内していただきました。
「公園の北側には原っぱが広がり、遊具もあるので、元気に走り回るお子さまや、のんびりと散歩する方々の姿がよく見られます。南側は森が多く、ちょっとしたハイキングや野鳥観察もできるエリアです。中央には池があり、水辺に棲むいきものに出会えることもありますよ」とのこと。さまざまな自然の表情が楽しめそうで、期待が高まります。
まずは北側、正門からすぐの場所にある「風の広場」。レジャーシートを敷いてピクニックを楽しむ人も多い、ファミリーに人気のエリアだそうです。桜の木が多いので、春にはお花見スポットとしても知られています。
少し歩いただけで、かわいらしい鳥のさえずりがあちこちから聞こえてきました。
取材に伺った3月下旬には、まだ桜はほとんど咲いていませんでしたが、鮮やかなピンク色の河津桜が出迎えてくれました。
地道な努力によって生まれ、維持されている景観
風の広場から南へ歩くと見えてくる「ススキ原っぱ」。その名のとおり、秋にはススキが一面に広がります。
実はこの場所、以前は砂利だらけで、草はほとんど生えていなかったそうです。堀内さん曰く「何年もかけてイネ科の植物だけを狩り残していった結果、ススキが自然に増えていき、いきものも人も楽しめる場所になりました」とのこと。今でも葛(クズ)のつるが伸びるとススキを倒してしまうので、地域の学校の協力を得て、クズを取り除く作業を定期的に行っているそうです。
ススキ原っぱの東には、小高い丘になった「太陽の森」があります。なんと、ここも2年ほど前まで鬱蒼とした森だったとか。
当時は日当たりが悪く、多様な植物が育つ環境ではありませんでした。生物多様性を高めるため、大きな木の伐採や草刈りを行い、アカマツの苗木が移植されたそうです。
「アカマツはもともと日本にたくさんあった木ですが、今は全国的に減少しています。その影響で、アカマツに卵を産むハルゼミというセミも絶滅危惧種になってしまいました。アカマツを育てることは、ハルゼミを守ることにもつながるんです」と、堀内さんが教えてくれました。
環境整備によって見晴らしがよくなった頂上の展望スペースには、「日だまりの丘」という名前がついています。
「この名前は『狭山公園キッズレンジャー』のこども達が考えた候補のなかから、投票により決まったものです」と堀内さん。キッズレンジャーは小学生向けの環境教育プログラムで、狭山公園のいきものを調べたり、環境を守る活動をしたりしています。太陽の森の草刈りも一緒に頑張ってくれたそうです。
野鳥が集まる森、多様性を取り戻した池
太陽の森を下り、太陽広場を通って、フクロウが棲むという「野鳥の森」へ入ります。
ここではフクロウだけでなく、たくさんの希少な鳥たちが巣をつくっています。鳥にストレスを与えてしまうので、大声でのおしゃべりや長時間の撮影は厳禁です。
野鳥の森の中にも、以前は竹藪が広がっていたそうです。高い木を残しつつ竹藪を刈り、里山を好む野鳥が棲みやすい環境がつくられました。
中央に積まれているのは、伐採した木の枝。細い枝ゾーンと太い枝ゾーンに分かれており、それぞれに種類の違ういきものが集まってくるとのこと。
野鳥の森を抜けたところにある宅部池(やけべいけ)へ。
以前はかなり水が濁っていたうえ、ブラックバスなどの外来種が増加していたという宅部池。池の水を抜く「かいぼり」を3度実施し、外来種を取り除くなどの作業を行ったところ、もともと池にいた在来種が増え、生態系が回復。水質も改善されてきたそうです。
宅部池からパークセンターへ戻る途中で通った「トウカエデの林」。秋は見事な紅葉スポットとなります。
キッズレンジャーたちがつくった巣箱が、あちこちの幹にくくりつけられています。巣箱はまだ設置されて間もないそうですが、これからどんな鳥が使ってくれるか楽しみです。
狭山公園では、いきものと人が共に楽しめる環境づくりのため、さまざまな工夫がなされていました。キッズレンジャーたちの活躍も頼もしいですね。
事前予約のいらないキッズプログラムや、誰でも参加できるガイドウォークも随時開催されています。
自由に散策するだけでも楽しい公園ですが、このようなプログラムやイベントを体験すると、もっと自然への親しみがわいてきます。ぜひ気軽に参加してみてください。
※営業時間、体験内容などが変更になる場合がございます。

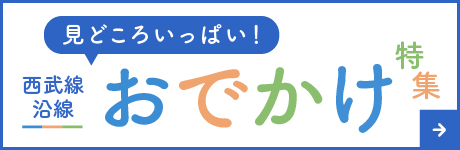
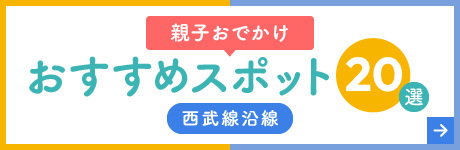
 LINEで送る
LINEで送る