酒造資料館で秩父錦の歴史を学ぶ
西武秩父駅からミューズパーク線循環バス「ぐるりん号」に乗り約20分。秩父の澄んだ空気のなかに佇む「酒づくりの森」に到着しました。敷地内には、酒蔵らしい風情の酒蔵資料館と洋風の観光物産館が並びます。
まずは酒蔵資料館へ。資料館では、江戸時代頃の日本酒造りの様子や矢尾本店の歴史について知ることができます。
「1749年に近江商人の矢尾喜兵衛が秩父で酒造業と雑貨商を始めたのが、矢尾商店の始まりです。その後、酒造部門を分社化して矢尾本店となりました。当初は秩父市街に酒蔵がありましたが、1994年にこちらに移し、観光酒蔵としてオープンしました」
そう話してくれたのは矢尾本店取締役 統括本部長の豊田哲也さんです。
酒造資料館内には、昔ながらの酒造りの工程が実際の道具を使用して展示されています。手動式洗米機やこし器など、展示に使用されている道具類は、すべてお店の蔵で大切に保管されていたもの。
昔ながらの道具はどれも今も現役で使用できるほど綺麗な保存状態。道具を大切にしながら酒造りをしていた人たちの様子が手に取るように伝わってきます。
資料館2階からは酒造りの様子が見学できます。「酒づくりの森」では、毎年12月3日に行われる「秩父夜祭」に酒粕や甘酒を出せるように、9月末から酒作りが始まります。取材に訪れた9月はまだ精米が始まったばかり。1階の貯蔵庫は実際に入って見学することもできます。
かつてはワインの醸造所だった観光物産館
資料館見学のあとは、同じ敷地内にある観光物産館へ。元はワインの醸造所だったという建物は、老舗ワイナリーの佇まいです。
館内には「秩父錦」をはじめ、矢尾本店で造られたお酒や秩父の名産がずらり。お酒の試飲も可能で、味わいながらお土産を選べます。
大吟醸酒の試飲は1杯100円というリーズナブルさ。丹精込めて造られたお酒を気軽に味わえるのがうれしいですね。
今回は豊田さんにおすすめのお酒をご紹介いただきました。
「秩父錦 MU-KU」(5,500円)は、「令和6酒造年度埼玉県春季清酒鑑評会」で県知事賞、「全国新酒鑑評会」で金賞を獲得した逸品。
「麻袋に醪(もろみ)を入れて、手しぼりで斗瓶(とびん)にとるという、昔ながらの手法を用いて造られたお酒です。この方法でとれるお酒は少量のため、本数も限られています」と豊田さん。口に含んだ瞬間に広がる上品さと爽やかさを併せ持つ味わいは、プレミアムな時間にぴったりです。
秩父錦純米大吟醸「至純」(6,600円)は、フランスで開催される日本酒コンクール「Kura Master 2023」で金賞を受賞。秩父産山田錦を100%使用し、ワインのような甘めでフルーティな味わいが特徴です。日本酒になじみのない方でも飲みやすいお酒です。
「秩父錦」の定番といえば「特別純米酒 秩父錦」(1,320円)。コクとうまみが特徴で、甘口でありながら酸味を感じる味わいはさまざまなおつまみと相性がよく、日常的にも飲みやすいお酒です。
オリジナルのクラフトビールやグッズも販売
米ぬかを使ったクラフトビール「FEST365」(各660円)も人気。一年中お祭りが行われる秩父ならではのネーミングのこのクラフトビールは、全7種類です。三峯神社の節分祭が由来の「2月3日のごもっともさま」や、秩父川瀬祭の「7月20日の水しぶき」など、それぞれの祭りのかけ声や様子が商品名になっています。なかでも秩父夜祭をモチーフにした「12月3日のホーリャイ」は黒ビールですが、酒粕を使用しているため飲みやすいと評判だそうです。
秩父錦オリジナルグッズも豊富です。酒造りの様子を描いたお猪口のほか、秩父錦の銘柄が入ったお猪口やショルダーバッグ、前かけなどを販売。本物の酒粕を使用した酒粕パックやフェイスマスク、入浴剤などの美容アイテムもあり、お土産選びが楽しい空間です。
秩父の良質な自然が生み出した酒
甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)に源を発する荒川水系の良質な水を使用し、秩父の名を冠した「秩父錦」は、地元の方々だけでなく全国の方々にも愛されています。
秩父の美しい森に囲まれた「酒づくりの森」で、秩父の自然と職人の技術が織りなした逸品に触れてみてはいかがでしょうか。
※価格はすべて税込
※営業時間、販売商品、価格などが変更になる場合がございます。

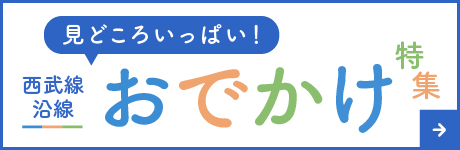
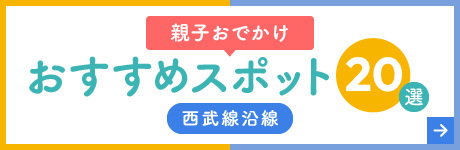
 LINEで送る
LINEで送る